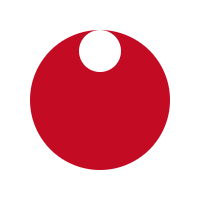ウディー・アレンの映画「インテリア」を見て感じた余白とは
文:NIPPON PROUD 森口 潔
映画「インテリア」とウディ・アレン
映画「インテリア」(原題 ”INTERIORS”)は、1978年に上映されたウディ・アレン監督・脚本のアメリカ映画だ。 ウディ・アレンというと前年の1977年の作品「アニーホール」でアカデミー賞の監督賞、脚本賞、主演女優賞(ダイアン・キートン)を受賞、さらに主演男優賞(ウディ・アレン本人)ノミネートという快挙を成した人物。
今の50歳代より下の世代にはピンとこないかもしれないが、間違いなく70年代から80年代の時代の寵児だった。 160cmと小柄でうだつの上がらない中年のようで、ちょうど吉本興業のミスターオクレのような風貌なのだが、アニーホールでは、当時のファッションアイコンになった共演のダイアン・キートンにも劣らぬファッションセンスを魅せるのである。黒のセルフレームの眼鏡、小柄のチェックのシャツ、ツイードジャケット、極め付きがプリーツの入ったチノパン。当時の流行に敏感なニューヨーカーには少なからず影響を与えたと思う。 発刊して間もない雑誌「popeye(ポパイ)」にも幾度となくそのファッションや行動、思想が掲載されたものである。
また、今では想像するのも難しいが、当時、情報発信の最前線には百貨店があった。 その中でも群を抜いていた西武百貨店のテレビCMで「おいしい生活」というヒットを飛ばしたことでも彼は、つとに有名だ。 この糸井 重里作のコピーはまだコピーライターなるものが世間に認知されてない時代に一躍彼とその職業に注目を集めたものだった。 そして音楽は矢野 顕子を起用、このコラボレーションは何かこれから新しい時代が始まるという予感を抱かせたバブル時代突入へのとば口でもあった。
映画や小説、音楽などは、数十年を経て再会するとかなり印象が変わることが多い。 この映画も1980年代に見た時は、何だか鼻もちならないインテリで富裕層の家族がいちいち問題を複雑にしていて全体的に暗く、長セリフで退屈な映画だなという印象だった。 インテリアの事やインテリア関係の仕事にもう少し描写があるものと思っていたが、それもあまりなく随分と落胆したのを覚えている。 (あらすじをチェックされたい方、は他のサイトをご参照ください。)
しかし40年後に再会してみると随分と違う姿を見せてくれた。 無論、主人公である一家の母エヴァが、知的な完璧主義者で、独善的な秩序を夫や三人の娘に対して強いてきたという流れは記憶にも確かだ。 その家庭は、あたかも完全無比に彼女に設えられたインテリアのようで、ある種の緊張感に満ちて、息苦しい。 彼女から受ける抑制は、やがて抑圧へと変わり、澱(おり)のようにそれぞれの家族の心に溜まってゆく。 そして夫君の小さな反逆から、外から見れば幸せそうな一家がガラガラと崩れて悲劇へと向かう。
今回新たに感じたのは、異なる強い意志や異なる人物が加わったときの脆弱さだ。 あまりに脆い。 もともと危ういバランスの上に成り立っていた関係性という設定はあるものの、ちょっとウディさん、プロットが甘すぎやしませんか? と突っ込みたくなるほどだ。 まぁそれはさておいて、もう一つ感じたことは、西洋と東洋、とりわけ日本とのインテリアに関しての大きな違いだ。 ラスト近くに次女のジョーイが独り言のように母に告げる言葉がある。「美しく家具が設えられた部屋、丁寧に造り込まれたインテリア、ひとつひとつがきちんとコントロールされ、そこにはいかなる感情も入り込む余地がなかった。私たち家族の誰の感情もまったくその余地はなかった。レナータ(長女)以外は」と。 つまり余白や余裕、あいまいさなどを排除したエヴァの世界を総括し、母に対する愛憎の感情を吐露したのだ。
もしエヴァが「陰翳礼賛」を読んでいたら
私が、洋と和の文化やインテリアの違いを表すときの万能薬が谷崎 潤一郎の「陰翳礼賛」だ。 これさえ例に引けば言いたい事の大方を網羅できる優れた作品。 昭和8年に発表された日本におけるエッセイの第一号と言われる本作は以前の照明器具「彦ペンダント」のブログでも触れさせて頂いた。
いくつかその主張を取り出すと、西洋の文化では可能な限り部屋の隅々まで明るくし、陰翳を消す事に執着したが、昔の日本ではむしろ陰翳を認め、それを利用することでその中でこそ生きる芸術を作り上げたのであり、それこそが日本古来の美意識の特色である。 汚れや闇を徹底的に排除しようとする進歩的な価値観を持つのが「洋」で、陰と曖昧さを好み、環境をあるがままに受け入れる諦めの姿勢が特徴的なのが、「和」の精神だという。
インテリアに当てはめてゆくと、見えすぎるものを闇に押し込めて、無用な物を排除してゆく。 つまり足し算ではなく引き算のインテリアという事だ。 そして障子戸などに象徴されるように、空間をあいまいに仕切って、余白を多く残してゆく。 無論この谷崎の随筆も洋と和を極端に比較するための一つの表現方法なので矛盾点も多々あるが、もし主人公のエヴァがこの文章に触れ、日本の「しつらい」も学んだなら結果は大きく変わっていただろう。
家族の一人ひとりを白日の下に晒し、寸分の遊びもないほどに統制してゆくことが家族がとるべき一択ではないことを知ったはずだ。 あいまいで大らかで、環境をあるがままの姿で受け入れるこの思想に触れていたならエヴァも幸せな人生をきっと享受でき他だろうにと思う。 まぁそうなるとこの映画自体も存在しなくなるだろうけど。